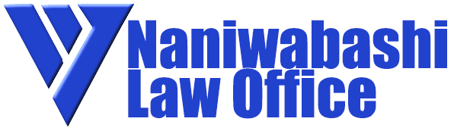Q8 当事者が主体的に問題を解決する方向に持って行くにはどうすればいいのですか。
A 紛争を起こしているのは当事者ですから、紛争で困っているのも当事者です。
紛争当事者は何とか紛争状態から抜け出したいとは思っているのですが、相手方に対する怒りや不満、解決するのにどれだけ自分が不利益を受けるかの不安、何でこんな紛争になってしまったのかの自責の念などで頭の中はいっぱいです。怒りや不満を表し相手方の非のあるところを次から次と取り上げて攻撃をします。攻撃を受けた方も相手方の非のあるところを取り上げて反撃をします。
この繰り返しを何回やっても紛争の解決にはつながりません。
では、どうすれば紛争解決の方向に向かうのでしょうか。
紛争当事者に紛争が解決できるのは当事者である自分たちだけであることと、これが解決なのだという状態(解決方法)を決定できる者は、他の誰でもないことを自覚してもらいます。
紛争当事者は、相手方に対して絶対相手が悪い、なぜあそこまで我儘が言えるのか通常の人間ではない等の感情を多かれ少なかれ持っています。
「お互い行き違いがあって相手方に対して、悪い印象をお持ちかも知れませんが、この話し合いの場だけでいいですから一時悪感情を横に置いて冷静に話し合いをしてみて見ませんか。」等と紛争当事者が自覚して冷静になれるよう対話を進行させます。
紛争で相手方の行為に対して自分が不満だったこと、悲しかったこと、腹が立ったことなど自分が感じたことを一人称で具体的に話してもらいます。
相手の行為によって自分が感じたことを具体的に伝えることによって、紛争当事者同士が相手の立場で、なぜそこまで嘆き悲しむのかが理解できお互いの違いを認め合うことが可能となるからです。
例えば、妻に子供の貯金を勝手に下ろして使ってしまった夫の行為を話してもらう場合です。
例1「仕事の付き合いでお金がいるのは分かるけど、どこの世界に子供のお金を持ち出して使う親がいるのよ。あなたなんて父親失格だわ。」
例2「仕事の付き合いでお金がいるのは分かるけど、子供のお金を持ち出して使ったと分かった時とても悲しかった。」
例3「仕事の付き合いでお金がいるのは分かるけど、子供のお金を持ち出して使ったと分かった時とても悲しかった。子供にどう話せばいいか途方に暮れたの。」
紛争当事者が自分の感じたことを一人称で具体的に話せるようになれば、お互いが被害者であり、また加害者であることに気づきます。
この気づきがあれば、当事者間に相手方の話を聞く気持ちが芽生えてきます。
次に紛争当事者が相手方の話を聞く気持ちになっても、年代、性、宗教、価値観、人生観に違いがあったとき、お互い理解や受入が困難な場合があります。
このような場合の違いはお互いに尊重し合い、そのうえでお互いの望んでいるものの本質はどこにあるのかを話し合います。
お互いの望んでいるものの内、一番大事なものは何かを双方で確認します。次にお互い望んでいるものの内なにを諦められるのかを確認します。これは互譲と言う事ではなく、自分が一番ほしいものを手にいれるための交換条件です。
進めてきた話し合いの中で、紛争当事者の間で起きた紛争の事実の確認ができ、紛争当事者が認識している一般常識あるいは倫理観が語られ、感情に流されること無く紛争を紛争当事者が認識したうえで合意が出来ない場合は対話による紛争解決より仲裁や裁判による解決が適していると考えられます。調停者は仲裁や裁判による解決方法を紛争当事者に理解してもらったうえで再度、対話による紛争解決を進めるかどうか紛争当事者に確認し続行するか打ち切るかの確認を行なうことになります。
Q1 ADRとは何ですか。
Q5 アメリカのメディエーションと日本の調停(司法調停)は同じですか。
Q6 同席調停と別席調停はどう違うのですか。双方のメリット、デメリットを教えて下さい。
Q7 理想的な揉め事・紛争の解決の仕方とはどんなものですか。
Q8 当事者が主体的に問題を解決する方向に持って行くにはどうすればいいのですか。
Q10 臨床心理から見たメディエーションにおける「聞く」ことの意味を教えてください
Q11 日本のメディエーションの場合同席調停と別席調停のどちらが妥当でしょうか
Q12 ADR促進法とは何ですか。