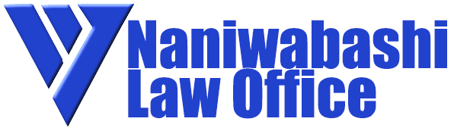Q4 裁判や調停(司法調停)だけではダメなんですか。
A 裁判は、過去の一定の場合について判断を下しますが、将来のことや裁判には馴染まない精神的なことなどについて裁判をすることは出来ません。また、裁判は勝つか負けるかになりリスクがあり、判決が出るまでに時間が掛かり、市民自身が直接コミットすることが難しく、裁判官の裁断で決定することになります。
一方、裁判所における調停は、将来のことや、精神的なこと、訴訟に馴染まないことも調停であればすることが出来ます。裁判所の調停は、調停の申立人から調停に至った原因等について聞き取りや質問をします。申立人の聞き取りが終わると代わって相手方が調停質に入室し,相手方からの聞き取りをします。紛争の実態を把握すると調停委員は、双方当事者が妥協できる落としどころを考えて、双方に対し互譲を求めます。この互譲を求められる条件が当事者双方の納得できる範囲に収まっているならば、この紛争はめでたく終了することになります。
ところが、この条件が当事者双方にとって、あるいは当事者の一方にとって全く呑むことの出来ないものであったならどうでしょうか。裁判所の調停委員は紛争の処理を裁判所という錦の御旗を楯にその解決を強いてきます。ここに裁判所の調停の限界が見えてきます。
調停に出頭した当事者のこんな発言をよく聞きます。曰わく
「あの調停委員さんは絶対に相手方の味方だ」
「調停委員さんは,私にばかり譲歩を強いて不公平だ」
これに対して,弁護士は,
「そんなことないよ。あの調停委員は相手方にも厳しいことを言っているはずだ」
「この事件の落としどころを考えて,両方に譲歩を迫っているはずだから,不公平というわけじゃない」
と弁護士が一生懸命調停委員を擁護しています。依頼人は,弁護士にそんなものですかと答えたものの,決して納得していません(このあたりは別席調停の難点です。Q6参照)。
ある事件を客観的にみると,だいたいこのくらいが妥当な落ち着きどころというのが見えてくることがあります。司法調停の場合も,調停委員の提案する調停案が概ね妥当であろうと思われる場合があります。調停委員は,両当事者がその案を受け入れるように,なだめたり,すかしたり,場合によっては強引に当事者の要望を押さえつけたりします。もし,この調停案と同じ結論に両当事者が自分の力でたどり着いたら(たどり着いたと思っていたら)どうでしょうか。きっと,両当事者は喜んで調停を成立させるでしょう。なぜなら,それは自分が勝ち取ったものですから(と思っている)。同じ結論であっても,人は押しつけられた(と感じている)ものには反発を覚えます。したがって,当事者は不承不承調停案に賛同しますが,心から喜んでいません。しかも両当事者ともそう思っている場合があります。こんな不幸なことはありません。
さらに,喜んで成立させた調停の場合,当事者は約束を守ります。自分で決めたことだからです。あるアメリカの社会心理学者の調査によると,紛争当事者の紛争手続に対する関与度が高ければ高いほど,その後の約束の履行率が高まるという結果が出ています。
この辺に目指すべきADRの途が見てきます。
Q1 ADRとは何ですか。
Q4 裁判や調停(司法調停)だけではダメなんですか。
Q5 アメリカのメディエーションと日本の調停(司法調停)は同じですか。
Q6 同席調停と別席調停はどう違うのですか。双方のメリット、デメリットを教えて下さい。
Q7 理想的な揉め事・紛争の解決の仕方とはどんなものですか。
Q8 当事者が主体的に問題を解決する方向に持って行くにはどうすればいいのですか。
Q10 臨床心理から見たメディエーションにおける「聞く」ことの意味を教えてください
Q11 日本のメディエーションの場合同席調停と別席調停のどちらが妥当でしょうか
Q12 ADR促進法とは何ですか。