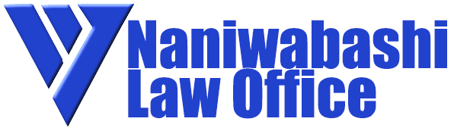Q11 日本のメディエーションの場合同席調停と別席調停のどちらが妥当でしょうか
A 事案の性格や当事者の個性等といった諸々の事情からケースバイケースで判断することになると思います。アメリカ流の同席調停を過度に強調することも,日本の文化風土の視点から同席調停を否定することも,極端すぎると思います。
ただ,一般的に言うと,紛争にいたるプロセスでは、当事者間での誤った理解や行き違いから、誤解や不信感が次々と生まれてくることが多いと言えます。それらはまるで「のど元に刺さった魚の骨」のように当事者を不快にさせます。メディエーションの現場では、まずこの「のど元に刺さった魚の骨」を取り除いて不快感をなくすことが大切です。お互いの誤解や不信感がそのままでは,メディエーションを行う環境としては適切でないからです。まずは、双方がこの問題を解決したい、あるいはしていかなければならないといった意識を持ってもらうことが、メディエーションを成功させるために必要となってきます。そのためには、当事者に自分の思いを語ってもらい、それをメディエーターが個別に聞いていくことで、その思いをくみ取り(受容)、当事者への理解を深めるといったことが効果的なのではないでしょうか。
メディエーションは、最終的には当事者間で解決策が見つかるということが望ましいでしょう。そのためには、どこかの時点でお互いが顔を合わせて話し合うという場面が望まれます。そうした場面を作り出すためには、メディエーターが双方からの話を聞き、それぞれの心の調整を進めていく必要があると考えます。第一には、メディエーターが何故当事者と会うのかを確認した上で、メディエーションについての基本的な説明を行う。はじめは個別で会い、メディエーターが当事者の思いをくみ取っていく。そこでは相づちを豊富に使い、当事者が自由にそして自然に話ができる環境を整えることが大切であす。しかし、常に話の中心を「この紛争をどのように解決していくのか」というところに戻していくということを意識しておくことも大切です。
当事者双方が、それぞれに自分の思いを十分に吐き出すと、最後に残ってくるのは「この紛争をどのように解決していくのか」ということになってきます。その段階までくるとメディエーターはしっかりと当事者と向かい合い、当事者が答えを出してくるまで付き添っていくのです。双方が答えを出せたとき、あるいはそのための協議が当事者間で行えそうなときが最終段階への移行となるでしょう。
Q1 ADRとは何ですか。
Q5 アメリカのメディエーションと日本の調停(司法調停)は同じですか。
Q6 同席調停と別席調停はどう違うのですか。双方のメリット、デメリットを教えて下さい。
Q7 理想的な揉め事・紛争の解決の仕方とはどんなものですか。
Q8 当事者が主体的に問題を解決する方向に持って行くにはどうすればいいのですか。
Q10 臨床心理から見たメディエーションにおける「聞く」ことの意味を教えてください
Q11 日本のメディエーションの場合同席調停と別席調停のどちらが妥当でしょうか
Q12 ADR促進法とは何ですか。