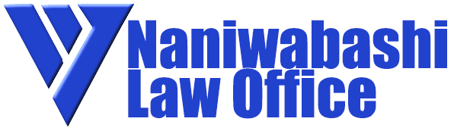Q10 臨床心理から見たメディエーションにおける「聞く」ことの意味を教えてください
A 臨床心理士の仕事の第一歩は「聞く」ということです。相談者の話に耳を傾け、相談の内容や相談者自身への理解を深めていくことです。また、相談者にとっては自分の思いを否定されずに聞いてもらえることで、ある種のカタルシス(浄化作用)が起こります。相談者にとって、それは心地よいものであり、気持ちも和らぎ楽になっていく体験です。そうした体験を相談者が積み重ねていくことで、臨床心理士との間に信頼関係が芽生え、自分自身の課題に向き合えるようになってくるのです。
今、ADRのメディエーションにおいても「聞く」ということがクローズアップされてきています。紛争という場では、お互いが相手の意見を聞くというより、自分の主張を押し通そうとしてもの別れになることが多い。そうした状況の中へメディエーターが入っていくときに、双方の話をじっくりと聞いて問題解決の糸口を見いだすということは、重要なポイントとなるでしょう。
確かに、メディエーターが両者に問題を事務的に整理し、何らかの基準に照らし合わせて妥協点を提示していくという方法もあります。しかし問題が感情のレベルでこじれるなどしたときには、双方に何らかのしこりを残すことが少なくありません。それは自分の思いがくみ取られた結果ではないという心理 がどこか働くからではないでしょうか。
人は誰かに自分の思いを話すことで気持ちが楽になったり、冷静さを取り戻したりすることができます。メディエーションの現場で、メディエーターがそれぞれの思いを個別に聞いていくということは、当事者双方についての理解を深め、そしてその紛争の理解を深めるということなのです。そうした作業を行うことが「自分の思いがくみ取られた」という心理につながっていく可能性があるのではないでしょうか。
もちろん、途中で裁判に持ち込まなければならない場合もあります。しかしここで重要なことは、当たり前のことですが、メディエーションは紛争当事者双方のものであって、決してメディエーターがその結果を決定づけてはならないということです。たとえ、メディエーターがそのメディエーションの見通しを持っていたとしても、その通りになるとは限らないし、当事者にその気持ちが少しでも伝わってしまうとメディエーターに対しての不信感を持ちかねないからです。最後の最後まで、メディエーターは聞き手にまわり、そして当事者が問題から逃避しようとした時にも、常に最終決定は本人にしてもらうということに徹することが、当事者の納得のいったメディエーションにするための重要な事柄なのではないでしょうか。
基本的に紛争は誰も望まない。しかし、その当事者になったときには誰もがその問題解決に立ち向かわなければならないのです。そして問題解決に立ち向かう人をいかに適切にサポートするかが、メディエーターに問われるのです。そして、そのまず第一歩は、「聞く技術」を身につけることではないでしょうか。
Q1 ADRとは何ですか。
Q5 アメリカのメディエーションと日本の調停(司法調停)は同じですか。
Q6 同席調停と別席調停はどう違うのですか。双方のメリット、デメリットを教えて下さい。
Q7 理想的な揉め事・紛争の解決の仕方とはどんなものですか。
Q8 当事者が主体的に問題を解決する方向に持って行くにはどうすればいいのですか。
Q10 臨床心理から見たメディエーションにおける「聞く」ことの意味を教えてください
Q11 日本のメディエーションの場合同席調停と別席調停のどちらが妥当でしょうか
Q12 ADR促進法とは何ですか。